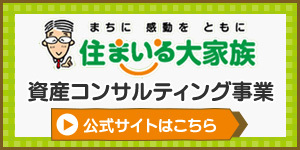2024年06月29日
不動産投資を学ぼう(2)(後半)
キャピタルゲインとインカムゲインの総和(後半)
10年間での投資判断としては、
・売却差益:投資額1億円-売却額6,000万円=△4,000万円
・賃 料 :300万円×10年=3,000万円
の合計で△1,000万円。投資価値は無しと判断します。
売却差益のことをインカムゲイン、もしくはインカムロスと言い、賃料や配当のことインカムゲインと言います。
投資判断の大原則は、「キャピタルゲインとインカムゲインの総和」です。つまり、賃料だけでは投資の判断はできず、建築費と賃料から割り出す利回りでは全く投資性を判断することできないのです。
相続税の節税を目的とした賃貸物件の建築提案にはこの「投資性の判断」がすっぽりと抜け落ちてしまっているものを散見します。先回お話しした様に、投資性が良いと単純に儲かるとかそういった話だけでなく、地主さんにとっては相続の問題も大部分を解決することになります。
「評価基準(KPI)」の話はまるまるセミナーのテーマにしたほど、私のコンサルでは大切にしております。評価基準として、「節税<投資性」ということを地主さんの相続対策としての大切だということをご認識いただければと思います。
次回は、投資性の評価基準(KPI)としてのある指標をご紹介しようと思います。
投資性の判断を「現金でいくらのものが、一定期間後に、いくらになるか」ということで判断するならば、収益物件に限らず、太陽光だろうと株、債権だろうと同一の指標で測ることができます。様々な投資商品を比較しながら、この指標をご紹介しようと思います。
2024年06月29日
不動産投資を学ぼう(2)(前半)
キャピタルゲインとインカムゲインの総和(前半)
「投資性」が良ければ相続の問題の大部分を解決することができ、そもそも運用収益で相続税の納税できれば節税対策する必要すらないというお話しを前回させていただきました。
つまり、「相続税の節税よりも不動産の運用の方が重要」≒「相続税の節税よりも投資性の方が重要」ということになります。
それでは不動産の投資性はどの様に判断するのでしょうか。不動産による相続税の節税対策を考える際は、相続税評価で考えますが、投資性の判断は「現金でいくらのものが、一定期間後に、いくらになるか」ということで判断します。前回少し触れた、建築費と賃料から割り出す利回りでは投資性を判断することできないと言った理由は、「現金でいくらのものが、いくらになるか」ということが、すっぽりと抜け落ちてしまっているからです。
5,000万円の土地に5,000万円の建物を建築し、建築費からの利回りが6%だった場合、賃料は300万円です。
運営費、税金等は考慮に入れないとして、10年間の投資性を判断した場合、どの様になるのでしょうか。
利回り6%で300万円、10年続くとして3,000万円儲かると判断して良いでしょうか。実際は下記の様になります。
5,000万円の土地に5,000万円かけた建物が10年後にいくらになっているかが重要となります。土地と建物で総額1億円の賃貸物件は、仮に賃料が一切落ちず、物凄くうまく売却できたとしても利回り5%の程度の収益物件としてでしょう。そうすると売却価格は300万円÷5%で6,000万円です。総額1億円の建物が6,000万円となってしまったので4,000万円損してしまったことになります。
(後半)へ続く。
2024年05月30日
不動産投資を学ぼう(1)
コンサル部門では一貫して、相続税の節税よりも不動産運用の方が重要だとお話ししてきました。
税金を抑えても、所有している人が大変になってしまうような不動産にしては本末転倒だという理由からです。そのため、どのくらい節税になるかを加味した上で、不動産運用の健全性より重視して精査してきました。キャッシュフローツリーを作成して、借入金の返済に
問題無いかはDCRで確認、空室にどれだけ耐えられるかはBERで確認、これを、賃料下落率を加味して長期で確認しました。これらは、地主さんの生活が不動産運用に直結しており、地主さんの生活を守るためのものです。
ただし、上記はあくまで長期的に不動産運用が問題なく継続できるか、破綻しないかどうかの指標であり、投資性を判断するものではありません。不動産運用の健全性を計るだけでも、これだけややこしく、訳の分からない横文字が出てくるので、さらにややこしくなる投資性の判断にまでは触れてきませんでしたが、投資性を判断することはとても重要です。
これは投資性が良いと単純に儲かるとかそういった話だけでなく、地主さんにとっては相続の問題も大部分を解決することになります。投資性が良ければ現金をたくさん残すことができます。地主さんにとっての現金の必要性に関しては下記となります。
- 相続税納税資金
- 資本的支出
- 分割資金
詳しくは
https://www.smile-shisan.com/blog/v/73/
相続税納税資金に関して、地主さんが賃貸物件を建築する目的として、相続税を円滑に支払うために、相続税額を落とすことを目的としている場合が多いですが、そもそも運用収益で納税できれば節税する必要すらない訳です。つまり、健全な投資運用が最大の相続対策となる訳です。
それでは不動産の投資性はどの様に判断するのでしょうか。建築費と賃料から割り出す利回りでは投資性を判断することは全くできません。次回から少しずつ、不動産投資に関してのお話をしていきたいと思います。
2024年03月16日
資産コンサルとは?
資産コンサルとは?
5年ほど前に、「資産コンサルティング部門」を立ち上げさせていただき、「山本の資産家通信」と銘打って情報発信させていただいております。
不動産業者なのに、なぜ不動産コンサルティングでないのか。そもそも資産コンサルティングとは何なのか。説明するのに分かりやすい案件がございましたのでご紹介します。個人の特定を防ぐため、また、分かりやすくするために一部情報を変更しております。
あるアパートオーナー様が、自分が亡くなった後、子どもさんの生活資金を確保するために、古くなったアパートの建替えを検討したいとご相談いただきました。不動産管理会社としてはありがたいお話でしたが、よくよくお話を聞いたうえで、私は別のご提案をしました。
理由としては、アパート建築は必ずしも生活資金の確保を約束するわけではないからです。アパート建築にはその後の「経営」が伴います。借入を返済しながら運用するには、不動産の運用判断の煩雑さ、収入の不確定さ、そして、基本的には経過年数が経るにつれ問題が増え、手残りが減少するものです。
このようなリスクを減らせないかと考え、代替え案として、下記の様な生命保険をご提案しました。自己資金、もしくは建替え予定地の売却資金により、一括加入をします。
・契約者 :親
・被保険者:親
・受取人 :子
・保険料 :一括3000万円
・保険金 :親死亡後、子が亡くなるまで毎月15万円(年180万円)
20年保証があり、仮に子が早くなくなってしまっても、その相続人に
20年間は保険金の支払いが行われる。トータルで180万円×20年
=3600万円の受け取り予定です。
この保険はドル建て債権で設計されているため、上記の様な好条件での契約が可能となりました。円建ての保険ではこのような条件は出ません。もちろんドル建てなので為替リスクがあります。ただし、お客様ご要望が「生活の確保」ということは、生活を確保するための物品やサービス購入するための「購買力」の確保と言えます。ご子息の年金が月額10万円の予定です。円高になれば円換算での保険金は少なくなりますが、円が強いということは円での購買力があるということなので円建てのフローである年金が購買力のリスクヘッジとなります。逆に、円安になれば円の購買力は弱くなりますが、円換算での保険金は多くもらえるということになります。
また、運用期間を最大化(今が一番若いので今保険契約)し、保険の条件を最大化するために一括で保険料を支払いましたが、保険金を受け取る際は、分割で受け取る予定です。これは投資の最適解のひとつである積立を、保険金を受け取るという出口でやるという設計です。こうすることで20年、30年の間に円安だったり、円高だったりの変動はあるものの均されて為替リスクは平均化されます。
保険金と年金の合計20万円~25万円程度あれば、仮に施設に入所することになったとしても経済的な問題はクリアできる予定です。賃貸物件の賃料では生涯にわたってこのような安定したキャッシュフローを確保することはできません。
資産コンサルティングとは将来の株価や為替の予想をするのではありません。投資運用の理論上の最適解や市場平均のリターンは把握していますが、市場平均を大きく上回る儲け方は分かりません。どの様な経済状況になろうとも、どちらに転んでも、大丈夫なように資産状況を調整します。
多くのお客様は問題に対する対策についての選択肢を把握されていません。それどころか何が問題かを把握できていないお客様が多いのが実情です。まず、漠然とした不安等をお話ししていただき、問題を具体化し、明確にします。次に、それに対する対策を不動産のみに囚われない選択肢をご提案したいと考えております。これが「不動産」コンサルティングではなく、「資産」コンサルティングとさせていただいております所以です。
もちろんこのような対応は、不動産業者だけでは難しい場合もあるので、他業種、他士業の方に協力していただくことも多いです。
当社の資産コンサルティング部門を窓口にご相談いただくことで、地主様にとって、業種を超えてワンストップで最大限のサービスをさせていただくことを目指しています
2024年03月08日
キャッシュフローツリー
当社は不動産の賃貸、売買、管理のみならず、賃貸物件建築、駐車場、住宅用定期借地、事業用定期借地等あらゆる不動産活用をご提案もさせていただいております。
今回は賃貸物件建築のご要望いただいた際に、当社コンサル部門がどの様な評価基準でご提案しているかの一部をご紹介させていただきたいと思います。
賃貸物件建築の際、最も確認すべきことは相続税がどうなるかではなく、賃貸運用に問題がないかです。借入の返済期間の30年~35年を通して返済に問題ないか、空室にどれだけ耐えられるか、意外にもこの2点さえも確認せずに建築されている場合があります。
そこで今回は、CPM(米国不動産経営管理士)の指標であるキャッシュフローツリーをご紹介します。ややこしいので少し簡略化しますが下記の様なものになります。
GPI(総潜在収入) :100
EGI(実効総収入) :95 ※ざっくり空室率△5%。
OPEX(運営費用) :△18
NOI(純営業収益) :77
ADS(元利返済額) :△53 ※返済期間30年
BTCF(税引前キャッシュフロー) :23
上記の数値を算出したうえで、賃貸運用の健全性を確認します。具体的には大きく2つ、借入金の返済に問題がないか、空室率に余裕があるかを確認します。
借入金の返済に問題がないか=DCR:NOI/ADSで算出。1.20以上ならOK。
今回の物件の場合、77/53=1・45のためOK
空室率に余裕があるか=BER:(OPEX+ADS)/GPIで算出。70%以下ならOK。
今回の物件の場合、(18+53)/100=71%のため若干空室率の余裕なし。
DCRとBERを算出した上で、次世代の方にも安心して所有し続けていただける物件とするために、今回の物件では頭金を入れていただきました。さらにDCRとBERの性質上の返済期間を長くすれば安全率は高まりますが、リスクを間延びさせないためにも返済期間は35年でなく、30年とさせていただきました。
直接建築業者様ではなく、コンサル部門にお問い合わせいただくことで様々な建築業者様の特色をお話しした上で建築業者様を選定していただき、建築業者様の提案のみならず、管理会社視点でのアドバイスをさせていただきことが可能です。昨今の建築費高騰状況でのフルローンでの建築の場合、DCRとBERが良くない場合、建築をおすすめしないということもありますが、賃貸物件建築の目的をよく考えていただき、ご検討していただければと思います。
なお、DCR、BERは、ご所有中の賃貸物件からも算出することができますので、興味がある方は一度算出されてはいかがでしょうか。- キーワード検索
- キーワードを入力
- カレンダー
- 月別の日記一覧
-
- 2024年06月 (2)
- 2024年05月 (1)
- 2024年03月 (2)
- 2024年02月 (1)
- 2024年01月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年09月 (2)
- 2023年08月 (1)
- 2023年04月 (1)
- 2023年02月 (3)
- 2023年01月 (5)
- 2022年12月 (1)
- 2022年10月 (1)
- 2022年04月 (2)
- 2021年12月 (1)
- 2021年10月 (1)
- 2021年09月 (1)
- 2021年08月 (1)
- 2021年07月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年04月 (5)
- 2019年03月 (6)
- 2019年02月 (2)
- 2018年11月 (1)
- 2018年10月 (3)
- 2018年09月 (8)
- 2018年08月 (5)
- 2018年07月 (20)
- タグ一覧